


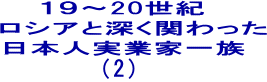

この間、私生活の面で繁司は妻・静子との間に5人の子供をもうけた。長男・敦武と次女・豊子は敦賀で、長女・清子、次男・剛、三男・省三はウラジオストクで生まれた。ウラジオストクで生まれた3人の戸籍謄本にある「ペキンスカヤ27番地」の建物は旧日本領事館の斜め向かいにあった(『異郷』19号10p参照)。ここは近藤が「商船組」を設立する以前の「林回漕店」の社員時代に住んでいた場所である。近藤夫妻は今でいう完全な共働きであった。子供たちの養育は、基本的には敦賀に居を構えた川邊虎・正夫妻、つまり静子の両親に委ねられた。長女・清子の話によると、幼稚園は敦賀で、小学校の数年をウラジオストクの学校に通っている。近藤夫妻も子供たちも敦賀とウラジオストクを行き来していた。16歳で結婚した当初の静子は写真で見るかぎり、日本髪に着物姿の普通の日本婦人だが、見る見る垢抜けて、洋服が似合う自信に満ちた女性に変身していった。彼女は社交家で華やかな女性であった。夫の仕事関係、出入りする船舶の船員の対応を見事にこなした。近藤繁司にとって、なくてはならない仕事上のパートナーであったにちがいない。近藤家の三男は母親が多忙で寂しい思いをしたと今でも子供時代を語るが、静子にしても、幼い子供たちを乗せて敦賀に向かう連絡船がウラジオストクの港を離れる時の、いつまでも甲板に立って手を振るわが子の姿が眼前から離れなかった、と語っていた。子供たちを手放した寂しさはいかばかりだったかと察せられる。
昭和3‐5(1928‐30)年に夫妻は、鉄道の連絡会議に出席のためモスクワに赴き、約1年間ここに滞在した。この間に二人は、パリ、ベルリン、ロンドン、ワルシャワなどヨーロッパの都市を訪れており、モスクワでは中条(宮本)百合子、湯浅芳子などとも交流があった。
「商船組」には妻・静子の兄弟の幾人かが働いていた。異色は、川邊家の次男・忠武で、敦賀商業のロシア語専科を卒業して「商船組」に入るが役に立たず、後に片岡弓八の経営するサルベージ会社に通訳として雇われ、地中海で沈没したロシア船ナヒーモフ号の引揚に関わった。
川邊家は関東大震災の後に繁司が東京の田端に買い求めた家に移住する。川邊家の四男・武彦と近藤家の長男・敦武は一つ違いで、共に本郷中学、法政大学に学び、生涯にわたり無二の親友であった。近藤家の長女・清子と次女・豊子は羽仁もと子が設立して間もない自由学園に通った。当時、女子教育の最先端をいく羽仁もと子の教育方針に繁司が共鳴したためだと聞く。田端の家には川辺、近藤両家の10名を超える子供たちが寝食を共にしており、朝は鐘の音で一斉に起床するなど、近所では有名な大家族だった。
前出の繁司の姉・キヌは、繁司と相前後して、大工である夫・高橋寿太郎とウラジオストクに渡り、ここで4人の男児をもうける。長男・誠一はウラジオストクの「日本小学校」を卒業している。夫・寿太郎が大正12年(1923年)にウラジオストクで死去したのに伴い、一家は日本に引き上げるが、その後の一家を経済的に支えたのはキヌの兄・繁司であった。誠一は繁司の支援で東京商科大学(現・一橋大学)に進み、次男・要は神戸の商業専門学校に学び、後に繁司が満州で設立する「近藤林業公司」で繁司の片腕として活躍することになる。
2.ハルビン時代
「たしか昭和7年だったと思います。近藤が当時終始往復していましたハルビンの出張所に行くのに、私は小さいトランク一つ持って気軽にウラジオを一緒に発ちました。国境近くになって、ロシア人の車掌が、今夜通過する場所は匪賊が出るかもしれないから灯は一切つけないようにと、まったく思いがけない警告に実に実に驚き、もしもの時を考え、東京の両親のこと、5人の子供たちのことがしきりに思い出され、一睡もしないで無事朝を迎えたときには感謝で一杯でした。ところが、ハルビン駅の近くになりましたら、昨夜襲撃を受けた列車が崖の途中に横倒しになり、死者、怪我人をタンカで運ぶ光景を見たときは慄然としました。私どもの列車はだいぶ遅れてハルビン駅につきました。その私どもの乗った列車が最後でウラジオ−ハルビン間の交通は途絶、こうして永年住み慣れた思い出多いウラジオとはまったく思いがけない最後のお別れとなりました」。この一文は、繁司の妻・静子が、生前「ウラジオストク会」の会報に寄せた手記の一部である。ウラジオストクを脱出した時の緊張した様子が目に浮かぶ。昭和6年は満州事変が始まった年であり、7年は関東軍がハルビンを占領した激動の年である。
満州事変の勃発により、北満との運輸連絡は断絶し、「商船組」は事実上経営不能に陥り、近藤はやむ無く満州での事業展開を模索することになる。おりしも、北満部沿線地区に林区を所有していたポーランド国籍のロシア人カワリスキーが、第一次大戦勃発後、ヨーロッパ市場への輸出の道を閉ざされるなど、世界不況の影響を受けて経営不振に陥り、近藤に協力を求めてきた。近藤林業の社史によると、林業経営に乗り出した際の状況について「満州国官憲および軍当局により懇切なる慫慂もありたれば、、、」と書かれており、外資の手にある利権を回収して北満森林資源を開発するという当局の意向が強く働いたことは確かである。従って、カワリスキーの事業が立ち行かなくなった真の原因は、帝政ロシアの崩壊、日本の満州進出、満州国の建国、その後の満鉄による鉄道の接収など、ロシア林業資本の置かれた状況の変化にある。
昭和7年9月に近藤林業公司を創立し、先ず亜布洛尼林区所有のカワリスキーとの間に、同林区の賃貸借および共同経営に関する契約を締結。同林区の権利の一切、すなわち、伐採権、森林鉄道、通信機材、製材工場、発電所、給水場などの諸設備を継承した。翌昭和8年には穆稜、ニ道海林河子および横道河子に対する賃貸契約を締結し、ただちに生産活動を開始した。
近藤が事業に着手した当初の林区は、前経営者の事業不振が長期にわたったことに加え、昭和6年に北満地区を襲った未曾有の水害により、惨憺たる状態にあった。再建は大規模なものとなり、回漕業で蓄積した資金が投入された。
その後、事業は急速に拡大し、昭和8年には穆稜林区の経営に着手、小興安嶺方面の森林開発のために三江木材公司の設立、ハルビン市内の馬家溝に木工場、馬具工場、松花江製材工場を開設した。異業種にも進出し、一面濱州線・喇嘛甸子に興農牧場を、ハルビン市郊外に農場を開いた。昭和12年には「ホテル・ニューハルピン」を設立した。昭和15年には北支木材株式会社を設立、北京に本社を設け、ついに中国本土にも進出を果たした。
近藤繁司の林業経営にはいくつかの特徴がある。
その一つは、カワリスキーから事業を引き継いだ際に、同社の従業員も引き受けたこともあり、亜布洛尼、横道河子、牡丹江の事業所には特に多数のロシア人従業員がいたことである。横道河子の「近藤林業公司・横道河子製作所」の「七キロ」をロシア人は親しみを込めて「コンドフカ」と呼んでいた。「七キロ」とは横道河子の鉄道駅を基点として森林鉄道が敷かれていたが、その七キロの地点のことを指す。ここには製材所をはじめ各種施設のほか従業員の住居もあり、一角にはロシア人が住む地域があった。
近藤はロシア人を重用し、ロシアの文化、風習、生活習慣を尊重した。各林区には従業員のためのクラブがあり、特にロシアの祭日などには華やかなダンスパーティーが開かれ、まさにロシア人の世界であった。彼はロシア語が堪能で、ロシア人にはロシア語で対していた。
また、近藤林業はかなりの規模の森林警備隊を有していたが、特に白系ロシア人で編成された警備隊は、関東軍の許可を得て銃器の携帯も許されていた。また、亜布洛尼近郊には青少年義勇軍の訓練所を持った。まさに“私兵”を有し、訓練まで行なう、そのようなことが可能であったというのは私企業としては異例といえよう。伐採は森林警備隊に守られながら進められた。
各林区ともに数千人から1万人規模の労働者が働いていた。切り出された原木は森林鉄道によって運搬された。昭和16年以降には、満州国政府、満鉄より延長200‐300キロにおよぶ亜布洛尼、頭道河子周辺の森林鉄道の運営を任されて、これに当った。
開業4年目に近藤林業は存亡の危機に立たされた。昭和10年の5月に関東軍特務部より「通匪、通ソ」の嫌疑がかけられ、一切の業務停止が宣告されたのである。それには、当時の満州国、軍が置かれていた状況、近藤繁司の前歴、ロシア人従業員を多く抱え重用していた姿勢などが影響したのではないかと思われる。近藤はこの間、従業員に給料を払い続けたと聞く。当時の状況下で「通匪、通ソ」の汚名を着せられるということは事業にとっても、また、家族にとっても耐えがたい苦しみであった。近藤はこの事態にまったく動じることなく、ひたすら事態の成り行きを見守ったという。この問題は現地で解決できず、本国の軍法会議に付された。関東軍にとっても近藤林業製品の長期にわたる供給停止は痛手であったに違いない。9ヵ月後にやっと業務再会の許可が下された。
近藤の事業は関東軍、その特務機関、満州国林野局、鉄路局、林区の警察の監視を受け、それらとの対応に絶えず追われていた。特に、昭和11年には「林場権整理法」が発動されて林区の伐採権が解消され、12年には「満州国、重要産業統制法」が公布されるなど、太平洋戦争に突入してからは、各林区は軍部の管轄下に入り、軍部からの監視官が常駐した。もはや近藤林業は自由な活動ができなくなっていた。
会社にとってはサイドビジネスであった前出の「ホテル・ニューハルピン」は大直街の高台、中央寺院、哈爾賓神社、博物館のすぐ傍、ハルビン駅からも徒歩10分という好位置を占め、ヌーボー・ルネッサンスの五階建で、客室数150余、和室もあり、室内は凝った内装であった。300人まで収容可能な宴会場、レストラン、バーなどの設備も充実。ホテルの経営には妻・静子も関わっており、内地で従業員雇用のための面接も彼女の役であった。
ホテル1階の正面右側の一角が近藤林業公司の本社事務所で、専用の玄関があり、「近藤林業公司 ЛЕСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С. КОНДО 」という看板が掲げられていた。近藤繁司は哈爾賓大街の自宅から歩いてここに通っていた。ハルビンを訪れる著名人の多くがこのホテルに宿泊し、お客好きな近藤夫妻の自宅の客となった宿泊客も多かった。現在は「国際飯店」と名称を変え、隣に高層な新館が建てられたものの、1997年に「哈爾賓市保護建築」に指定され、昔のままの外観を保っている。
[以下次号] 参考文献は次号の文末にまとめて示す。