

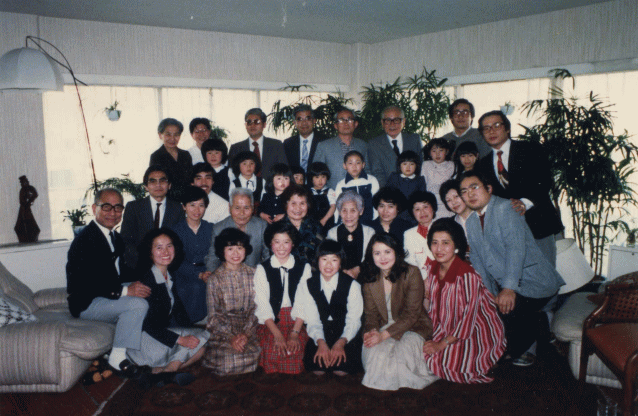


筆者の父・高橋誠一は、1936年に近藤繁司の長女・清子とハルビンで結婚した。誠一の母は繁司の姉に当たる。二人は幼馴染みで、いとこ同士の結婚であった。父は大学を卒業してハルビンの近藤林業公司に入社した。インテリの苦悩と弱さを悲しいほどもっていた人間であった。1938年に小興安嶺の森林開発を行う三江木材の所長に就任、冬は零下数十度、夏は蚊群に悩まされるという過酷な自然条件と治安の悪い林区に、200人の森林警備隊に守られながら2000人規模の労働者によって原始林に分け入る作業は彼にとって想像を絶するものであったに違いない。腎臓を侵され1938年8月、30歳の若さで亡くなった。その時筆者は1歳、父の記憶はまったくない。
近藤繁司は事業の展開に必要な人材に絶えず腐心していた。唯一近藤繁司の片腕となったのは、高橋誠一の弟・要であった。要は横道河子林業所の所長を、その後、亜布洛尼林業所の所長も務め、兄・誠一の死後、三江木材の所長も引き継だ。
終戦の前の年に筆者は、母・清子が関東軍司令部勤務の陸軍中尉・土方雄武と再婚するのに伴い、東京からハルビンの近藤繁司の家に移った。この家は、哈爾濱大街の中央寺院の隣地にあり、手入れの行き届いた広大な前庭、玄関脇には蔦で覆われた二階建てのバルコニーがあった。春になると咲き乱れるライラックの放つ芳醇な香り、玄関先に置かれた鉢植えのゼラニュームの真紅が特に印象に残っている。玄関を入ると左側に薄暗い書斎があり、右側には四隅に応接セットが置かれ、大理石のマントロピース、その対面には天井まで、壁面にはめ込まれた大鏡のある応接間。応接間に続いて来客用のダイニング。奥に音楽室。そこには古い自動ピアノがあった。このピアノはロール状の紙に穴が開いていて、それをピアノにセットすると鍵盤が動いて曲を奏でる仕組みになっていた。
家にはロシア人の使用人が4人いた。強く記憶に残っているのは近藤繁司の末娘・京子のニャーニャ(乳母)だ。京子は近藤繁司57、静子46歳の時の子供である。典型的なロシア人の世話好きな女性で、夜は8時になると何があろうとベッドに入れられる。もう一人は物静かな夫人で、裁縫室に通ってきていた。子供の服などを縫ってくれていて、いつも京子と筆者はかわいいお揃いの服を着せられていた。カラウリと呼んでいた門番が庭の中の別棟に住んでいた。終戦直前、ソ連軍が国境を越えて満州に侵入すると、ラジオで知ったのだろう、急に威張りだした。もう1人は、毎日通ってくる庭師で、背が高く無口で黙々と働いていた。家ではロシア人にはロシア語で対応していた。そのほか中国人のコックや、日本から来ていた行儀見習いの女性などがいた。
祖父・近藤繁司は筆者を養子として迎え、小学校には「近藤和子」の名で入学した。毎年夏になると本宅を閉めて一家はスンガリー対岸にある別荘で過ごすのが常であった。筆者が小学校に入ってからは、学校が休みになるまで、朝は祖父とスンガリーをボートで渡り、迎えの車で花園小学校の近くまで送ってもらった。授業が終ると歩いてホテル・ニューハルピンの一階にある本社の社長室で祖父の仕事が終るまで待ち、一緒に帰った。祖父との忘れられない思い出である。
(3)終戦
近藤一家は終戦を哈爾濱大街で迎えた。男たちはみな招集され、残されたのは女子供ばかり。7歳の筆者を頭に1歳未満の乳飲み子まで7人の子供がいた。
ソ連軍は終戦後間もなくハルビン市内に侵攻、家の前の空港に通じる道には、長い銃砲をつけた巨大な戦車の列が突如出現し、間もなくマンダリン(自動小銃)を担いだ狙撃兵が大挙して家に入ってきた。司令官だろうか、近藤繁司が歓迎の意味を込めてお酒を勧めると、兵士に囲まれた近藤に毒味をさせてから杯を空けた。翌朝の立退きを命ぜられたその夜は、家中が荷造りと部屋の片付けに追われ一睡もしなかった。近藤繁司は、明け渡す家がすぐに使えるようにと清掃、ベッドメーキングまでを指示した。翌朝、使用を許されたトラックの荷台に荷物と一緒に家中の者が乗込んで住み慣れた家を後にした。
行き先は近藤林業公司の馬家溝工場であった。この工場は馬具、戦争末期には模擬飛行機などを製造していた。模擬飛行機とは敵の目をごまかすために飛行場に並べておく木製の飛行機である。馬家溝河を挟んで広大な土地に工場、資材置場、社員寮などが点在し、近藤一族はここの社員寮に入った。ここには近藤林業公司の横道河子、亜布洛尼、佳木斯等の林区から避難してきた人々がいた。なかには『マルーシャ』の著者中林庫子氏一家、『ハルビン物語』の著者作田和幸氏の一家もいた。周囲を塀に囲まれた敷地の入り口には、近藤繁司が雇った銃を持ったロシア人の私兵がいた。戦後のハルビンで、この場所だけが唯一ソ連進駐軍が許した安全な場所であった。
終戦後、奥地から避難民がハルビン市に殺到し、軍人も役人もいなくなった後をどうにかしなければならないと立ち上がったのが民間人であった。そこで、ロシア人と対等に交渉ができる人物として、近藤繁司が担ぎだされた。9月に入ってすぐ、ソ連駐留軍司令部の許可を得た「近藤難民救済会」(ロシア語名:オルガン・コンドウ)が組織された。「ОРГАН КОНДО」の腕章を付けた関係者は占領軍に認められていた。近藤には街にあふれている裸同然の避難民を冬将軍が迫る前にどこまででもいい、南下させたいという切羽詰まった思いがあり、会長に就任してすぐ旧満鉄と交渉を始めた。日本人には権限がなく、ソ連軍司令部、それに急に権限を得たロシア人職員との困難な交渉を重ねた結果、やっと20両の貨車を4回出すことに成功した。
当時、近藤が一人で行動をしているのを見た旧満鉄幹部の間で、誰かボディーガードをつけないと危険だ、ということになり、ハルビン駅の事務助役だった27歳の大関巌氏に白羽の矢が立った。それまで近藤繁司とは一面識もなかった大関氏は、その後8年間近藤家と運命を共にすることになる。
1945年11月近藤繁司は馬家溝の避難所でソ連兵に逮捕された。戦後最初の逮捕だったが、本人には行き先も目的も明かされないまま1カ月後に無事釈放された。1月7日の誕生日には避難所内で還暦を祝う会が開かれた。2回目の逮捕も馬家溝の避難所で1946年春、幹部を集めて会社の後処理について会議をしていたところにソ連兵に踏み込まれた。近藤を始め高橋要等が連行され、ハバロフスクに送られた。後ろ手に縛られてトラックの荷台に乗せられ、連れ去られる光景は今でもはっきり脳裏に焼きついている。近藤夫妻の部屋は封印された。
数ヵ月経ったある日、封印をはがして1時間以内に荷物をまとめて移動するようにという連絡が入り、連れて行かれた家にハバロフスクの抑留から戻った近藤繁司がいた。数ヵ月ぶりの再会であった。この家は、長春鉄路公司林業所の社宅で北京街にある五部屋からなる一軒家で、裏庭が広く、ここで鶏、豚、山羊などを飼い、本格的に野菜作りに励んだ。隣はソ連の憲兵隊長の家で、二つの家の間にある背の高い板塀が二枚はずれて、なにかの時には助けを求めることができるようになっていた。つまり隣の保護下にあったのだ。
近藤繁司は長春鉄路公司林業所の事務所に通い出した。事務所は奇しくもかっての近藤林業公司の本社オフィスであった。出勤しても決まった仕事があるわけではなく、大関氏と一緒に出勤し、ロシア語の新聞を隅から隅まで読み、時には相談に来る人の相手をしていた。給料は高粱など現物支給であった。
1946年の8月中旬から邦人の日本への帰還が始まった。しかし、近藤繁司は帰国することはできないと、ある筋から言われていたので、家ではその気配すらなかった。親族、社員は帰国し、近藤夫妻、長女・清子、三女・京子、清子の子供2人(筆者と妹)と大関巌氏が残った。
1946年の春、ソ連駐留軍はハルビンから撤退し、その後中国共産党の八路軍、国民党軍と不安定な時期を経て中国共産党が政権を確立、政情は安定した。この間、近藤は何度も逮捕された。三女・京子は母に連れられて格子越しに父親と面会した強烈な印象を忘れていない。こんなこともあった。終戦まで家にいた中国人のコックが、北京街の家に訪ねてきて「太々(奥さん)が食事を作っているのは見ていられない。給料はいらないから」と毎日通ってきていた。ところが、ある日、コックの息子で八路軍の兵士が、近藤を逮捕しに来た。父親はそれを苦に自殺した。
ついに恐れていた日が来た。1948年9月4日、近藤は長春鉄路公司林業所の事務所に出勤したまま行方不明になった。比較的治安が安定したこともあって、片道10分程の道のりを大関氏を伴わず一人で通勤するようになっていた。夜になっても帰らず、事務所を4時に出たあとの足取りがまったくつかめない。ソ連の領事館、ハルビン市役所、公安局、各地区の警察署、留置所などを静子は大関氏とまわった。それは、妻・静子の日課となった。ソ連領事館の対応はていねいだったが、中国側にはまったく相手にもされたかった。なんの情報もないまま、年月が過ぎた。
終戦後8年目に、中国の建設に協力するために残された医師、技術者、旧満鉄関係者の引き揚げが決まった。私たちは近藤繁司を失ったまま、1953年5月8日、日本の土を踏んだ。
帰国後、近藤静子は1983年、88歳の天寿を全うした。近藤繁司亡き後の困難な生活のなかでも「今が一番幸せ」というのが口癖だった。高橋要はソ連貿易の商社を設立し黎明期のソ連貿易に活躍した。筆者もその会社に勤め、モスクワに2年駐在した。近藤家の三女・京子は夫とともに会社を設立し、現在も対ロ貿易に活躍している。
近藤繁司はいろいろな意味で稀有な実業家であったと思う。若くしてウラジオストクに渡ってから戦後ハルビンで行方不明になるまで、日本に定住することはなかった。ロシア人を理解し、敬愛していた。敗戦によって彼は一瞬にしてすべてを失った。しかし、歴史的に見れば関東軍に協力した侵略者という位置づけを免れないのだろうか。やりきれない思いである。敗戦の年の春ごろから、家の周囲に住んでいた関東軍幹部が一人また一人と家族を連れて内地に引き揚げていった。せめて家族だけでも帰国させたらと近藤繁司に進言した人もいたが、従業員とその家族がいる限りそれはできないと応じなかった。財産を内地に移すことも一切なかった。
近藤を知ろうとすればする程、あまりにも不可解な点が多い。まず、ウラジオストクでソビエト政府との間に8年間の埠頭の使用許可を得られたこと。満州では武器携帯を許されたロシア人の私兵を持てたこと。終戦後のソ連占領下で「近藤難民救済会」を組織しかなりの権限が与えられたこと。馬家溝の工場跡地を治外法権として使用を許されたこと。そして最後に、誰がなんのために近藤を連れ去ったか、ということである。これらの問いに答えが出る日はくるのだろうか。
「近藤一族」執筆にあたっての主要参考文献は以下のとおり:萩原敏雄著『日露国際林業関係史論』、近藤林業公司『創立十周年記念写真帖』、太平洋戦争研究会『図説満州帝国』、中林庫子著『マルーシャ』、 長谷川潔著『北満州抑留日本人の記録』。その他に中林庫氏、大関巌氏、近藤清子、近藤省三の談話を利用させていただいた。