今回突然、相川さんから何か書いてと依頼があった。
そこで考えて、既にいろいろ諸先輩から通訳のありかたについて、有益な意見が沢山だされていることだろうから、重複を避けて、というよりは逃げをうつことにした。
人生には沢山の“出会い”がある。それによって人生は豊かになる。まして我々のように二つの言葉を話す者には、二倍の豊かさが贈られる。有難い職業だと思う。
これから思いつくままに書くのは私の体験を語ることで、若い方々の見聞が少しでも深くなればいいなという思いからだ。通訳者は知ってることの方が知らないことよりは訳しやすいから。
私は仕事の中でリヒテルとムラビンスキーと出会った。それだけでこの世に生を受けた価値があったと運命に感謝している。
今回はリヒテルが主催した型破りの(我々から見れば)音楽会を紹介しよう。
これは彼亡き後もつづいているが、毎年十二月になるとプーシキン美術館の白いホールで
≪ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА≫いう音楽祭がおこなわれる。これはあるテーマが決められて、それに基づいてのコンサートだ。
例えば“ロシアの画家と音楽”、“モーツァルトの世紀”、“イギリスの音楽”、“二十世紀の音楽”、“ロマンチシズムの世界”、“チャイコフスキーとレビタン”と云った具合である。
例えば“ロマンチシズムの世界”の場合はこうだった。
舞台には十九世紀のサロンがあった。部屋の中央にはバルコニーへ通じる開き扉があり、そのガラスは雪の結晶で覆われ、窓枠には雪が積もっているという凝りようである。
リヒテルは多分ウィーンにあるサロンをイメージしたのだ。舞台上にはサロンの客達が男女あわせて四十人くらい、ピアノにむかうリヒテルをデッサンする人、ヴァイオリニスト、ピアニスト、舞台まわしのせりふを言う人と役割も決まっていた。
サロンにいた美術館長のアントノワさんがリヒテルに言った。
「この時代のサロンコンサートでは即興的にいろいろな趣向がこらされたそうですね。」
白いホールの(キャパシティーは700人くらいか)客席から声がかかる。
「聞こえません。マイクを使ってください。」
「十九世紀にはマイクはありませんでした。耳をすまして聴いてください。」と、すかさずアントノワさん。
「そう、例えばこんなふうに。」と、リヒテルはサロンを見渡してピアニストを探しだし、デュオ“東方の絵”の演奏が始まった。この即興的パガニーニのあと、女性が立ち上がった。
「本物のパガニーニもきいてみたいですわ。」この人は女優で、さすがに声がよく通った。
「誰かヴァイオリンの弾ける人は?」リヒテルの問いに、これまた偶然にも該当者がいて、ヴァイオリンが響く。こうやってモスクワの十二月の夜はふけていった。
サロンの客である我々にはリヒテルからのきびしい要求があった。「みやびやかな立ち居振舞いをして十九世紀の雰囲気をだせ。プロレタリアートではないのだ。」と。
ツルゲーネフの主人公のようなロシア美人から、イギリス、フィンランド、エクアドル、一人の日本人の“その他大勢組”は、とても緊張した。
次の日はショパンの日。舞台のまん前にウィーン風な四方見の盛り花がおかれていた。やおらマエストロはコーカサス風のナイフをもちだして、楽譜(小道具)の封印を切ってから弾きだす。曲のはざまに客にシャンパンが出され、彼は一口飲んでシャンパングラスをピアノの上において弾き始めた。弦が切れると思うほどのダイナミックな演奏にグラスが倒れるのではないかと、私は音楽どころではなかった。
だが、衣擦れの音も聞こえそうなデコルテやミンクのストール、沢山の燭台の灯が舞台を照らし、サロンは華やかでエレガントだった。かててくわえてリヒテルのアイデアで、客席にはゲランのミツコがふんだんに撒かれ、観客は熱気と芳香に包まれて彼の音楽に埋没していた。(当然我々はミツコをより多く自分にふりまいて着服したけど。)
この日のあり方にはモスクワでは賛否両論だったが、リヒテルの変幻自在の一面がみえて、私はこの“あそび”に、おおいに共鳴した。

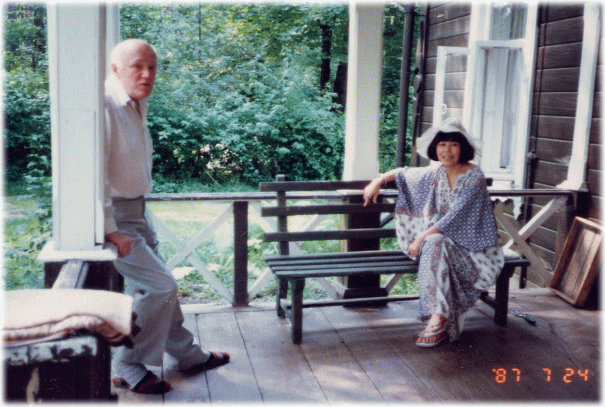

会報29号(2000年10月10日発行)から